|
『職業としての官僚』(嶋田博子、岩波新書)
https://amzn.to/3ZlwTuN
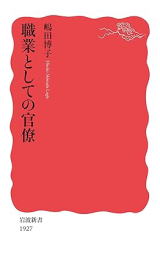
筆者は、元人事院(*1)人材局審議官、現在は京都大学公共政策大学院教授。
嶋田教授の人事院での最初の仕事は公務員への週休二日制の導入であり、最後の仕事は国が障碍者法定雇用率を達成する筋道をつけたことであった。国家公務員として実績を残した嶋田教授は「運命の不思議さ、力強さ」に導かれて学者となった(「あとがき」参照)。
現在、各種のメディアでも頻繁に報道されているが、国家公務員に優秀な人材が集まらない。また若手がどんどん辞めていく。国家的危機である。
国家公務員に再び多くの優秀な人材を呼び戻し、天職として快適な環境で長く働いてもらうためには、この本は避けては通れない。
筆者によれば、本書の目的は、官僚の①「実像」、②「理念」及び③「達成の筋道」を示すことにある(「はじめに」参照)。
すなわち、本書には、現在の国家公務員の状況(第1章「日本の官僚の実像」―どこが昭和末から変化したのか)だけでなく、平成以降の公務員制度改革の歴史(第2章「平成期公務員制度改革」―何が変化をもたらしたのか)、外国の公務員制度と日本との比較やその背景となる歴史・理念等(第3章「英米独仏4か国からの示唆」―日本はどこが違うのか)が書かれており、今の国家的危機からの脱出の鍵やヒント(第4章「官僚論から現代への示唆」―どうすれば理念に近づけるのか)が示されている。
筆者の願いは、「はじめに」の最後にあるように、①「中央官庁の仕事に人生を賭ける価値があるのか真剣に考えている人々(注:国家公務員になることを真剣に考えている受験生)に、大まかな見取り図を渡すこと」、②「その任にふさわしい資質がある者が官庁で活躍するのを応援したいと望む人々(注:国家公務員になる資質・実力・見識のある受験生の合格と活躍を応援する大学・予備校関係者や家族・親族)に支援のためのツールを託すこと」及び③「官僚という職業を選んだ人々(注:国家公務員、特に若手)が、天職を見出して幸福な人生だったと納得できること」である。
したがって、本書は、国家公務員受験生や国家公務員だけでなく、国家公務員や国家公務員制度に関係や関心を持つ人が、ぜひ読まなければならない必須の書であるといえよう。
著者は、本書は「公務員に採用されるテクニックを伝えるガイドではない」とはしている。
しかし、国家総合職を目指す受験生には、まず、以下の頁を読んでいだだきたい。
-
6~10頁には採用者が訪問者を見るポイントが簡潔に書かれている。以下、幾つか挙げてみる。
- 席次よりも対人能力が大事である(対人能力が徹底的にチェックされる)。
- 府省庁の仕事の大枠や方向性を的確に掴んでいるか。
- 相手の意図を瞬時に理解して的確に返せる能力があるか。
- ストレスに強いか。
- 様々な立場の人々と上手くチームが組めるか。
特に、重要要素としては、
- 官庁の仕事の意義や地方自治体・企業との異同を掴んでいるか。
採用の決め手になるのは、
- 「省の担う価値を共有できるか」(相性。「婚活に近い」)。
さらに、60~63頁には採用時の着眼点が詳細に書かれている。
「今後の社会や人間への強い関心を持っているか」が採用の決め手で、「部下の統括や組織管理ができるかという人間性もチェックされる」が、「省庁ごとに背負う使命や重視する点には違いがある」ので、「自分自身の価値観との相性を考えて募集することも大事」であるとのことである。
ここには、他にも重要な着眼点がたくさん書かれている。ここも受験生にとって必見である。
- 117~119頁では、応募者層の分析がなされている。
資格試験予備校や大学の公務員講座では目的意識のある人ばかりなので、私自身はあまり気づかなかった(もっとも薄々は感じていた)が、「応募者の二極分化」が進んでいるとのことである。
「安定志向型が多数だが、公益のために働くという目的意識を持ち準備も積んだ優秀層も少数ながらいる」というという指摘には救われた気分になった。
東大理Ⅲを頂点とした医学部志向の強い灘高校でも、「『この日本を何とかしたい』という東大文Ⅰを目指す学生が一定数はいる」という校長先生の話を以前ネット記事で見たことがあるが、それを思い出した。
しかし、いつまでも目的意識のある受験生(絶滅危惧種?)に期待するわけにはいかない。
根本的には、総合職の働き方改革と大幅な給与(基本給)アップが必要だと考える(*2)。 繰り返しになるが、本書は、①国家公務員、特に人事院を希望する人(今年、私の教え子の最終合格者に本書を勧めたところ、無事に人事院で内々定に至った)、②国家公務員を目指す受験生を支える家族や大学・予備校関係者、③公務員制度に関心や関係がある方、特に国会議員(国会での質問に関連した国家公務員に対する非人道的な対応に対する反省も含め、早急な公務員制度改革に着手していただきたい)には必携・必読の力作である。
それにとどまらず、官僚に対して偏見といわないまでも断片的な知識しかない方や無関心な方にも、ぜひ「結び―天職としての官僚」に掲載された嶋田教授と同世代の官僚の「仕事から得られた喜びの思い出」を読んでほしいと思った。
そこを読むと、等身大の真面目に仕事に取り組んでいる官僚の意識や実像がわかる。
「世のため、人のため」という理念を持ち、厳しい現実に立ち向かっている官僚がいるというのは、国民にとって非常に心強い。
このような官僚が「絶滅危惧種」とならないよう、国民や国民の代表者である国会議員は、厳しい現実に直面している官僚に対する温かい眼差しと協力が必要だ、と改めて本書を読んで思った。
【追記】
(*1)人事院面接と嶋田教授
人事院面接は国家公務員試験の2次試験にある(面接官は3人。真ん中は人事院の職員で主審、両側は各省庁の人事担当職員で副審である)。総合職の春試験では約15分間の人事院面接に全体の15分の3という高い配点が与えられている。
かつて人事院面接は、関西→関東の順で行われた(今は同時に開始)。
以下は、かなり前に、Wセミナー(京都校)渡辺ゼミ生A君が話してくれた彼の知人B君の話である。
ゼミ生A君の知人B君(京大生)は、人事院面接で、学生時代に一番打ち込んだ学問として哲学を挙げていた。
B君は、「哲学の話など面接官はあまり知らないだろう、だから、面接官に詳しくは聞かれないだろう」と思って面接に臨んだ。
しかし、意外にも、彼は真ん中の女性面接官(主審)からかなり高度で専門的な質問をされ、主審を納得させるに足りる十分な回答ができなかった。
すると、彼は主審から、鋭く勉強不足を指摘された。
後日、その哲学に造詣が深い面接官は、土・日の間に関東に移動し、月曜日から東京でも、(大型台風のように)鋭い突込みで猛威を振るい、受験生に大いに恐れられた。
その話を数年前に京都校でも話したところ、京都大学公共政策大学に所属するゼミ生C君が、「その面接官は人事院を退官されて今、京大におられる嶋田先生ではないかと思います。」と指摘してくれた。
その面接官が嶋田教授だったのか、真偽は不明である。
だが、嶋田教授が哲学や社会思想について深い教養を持っておられること、崇高な使命感をもった優秀な国家公務員だったことは本書(特に、第4章「官僚論から現代への示唆」、「結び」と「あとがき」)を読むとよく分かる。
(*2)メディアと公務員制度に対する姿勢とアプローチ(私の経験)
かつて私はA社の雑誌『A』の取材を受けた。
私は、雑誌『A』に、①日本の公務員は本省課長以上になると世界一(注:当時の為替相場による)給与は高く(注:そのせいかどうかはわからないが、総務省が毎年、発表する国家公務員のボーナスの数字は、本省課長以上の管理職を除いたもので、実際よりはかなり低く公表されている)、フランスと並び世界一の水準であるが、②それに比べ、若手の公務員は過重労働で、残業手当も全額支給されるとは限らず、大手商社などに比べて給与も安いので、何らかの手を打たないと優秀な人材が集まらなくなると話した。
元ゼミ生だった鈴木憲和農林副大臣が農水省で内定を得たのは平成16年だが、確か、その年、他の学部の東大生はいるが法学部からの内定者は彼一人だけだった。20年前から東大法が衰退する兆候はあった。また、同じくその頃だったと思うが、厚生労働省ではある期の女性のキャリアが全員辞めてしまったと聞いた。すでに以前から若手(特に女性)が辞める兆候はあった。
しかし、当時流行していた公務員バッシングの一環としてか、雑誌『A』は①のみを取り上げ、『噂の東京マガジン!』というテレビ番組で何と金賞を獲得してしまった。当時、私は大変、驚くと同時に、非常に落胆した。私が伝えた若手の悲痛な叫びは、結局、国民には届かなかった…。
数年後、雑誌『T経済』から取材を受けた。その時、上記の経緯と②を話した。『T経済』のその時の特集は「公務員が如何に恵まれているか」というスタンスだったが、②若手の不遇な状況と待遇改善の必要性について小さなコラムながら書いてくれた。
その『T経済』の記事の影響かどうかはわからないが、その後、若手の給与は少しだけアップした。
(2024/12/3 渡辺 一郎)
|


